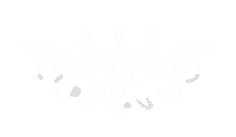どこで生まれたのかわからない。あの街の光はなんなのか。水面に揺れるピンクだとか黄色の光にはどこか中毒性がある。
湾岸沿いを歩く女と男の声は振動してピンクの色を水面に散りばめる。それは地上にある桜という花に似ている。
女は転んでそこから動かなくなった。1990年2月。夕方から降った雨は地面と水面を平らにした。今、女はこの世界で二人いるように見える。ふわふわした白く温そうな襟巻が悲しそうに風を受ける。
女の磨き上げられた背中を眺める。この世界で生きられないのはあの女も同じなのだ。男が戻ってくる。男は煌びやかなイヤリングを拾い上げ女へと差し出した。
あれが欲しい。腕の時計が時を刻む。ここから出て行く。そっと海に沈む身体は鼓動を早くして、その先の未来に発熱した。
自身の出自をたどり交差する関係を、平成という時代を振り返り写真と映像を用い表現しました。「何かを引き換えにしてでも手に入れたい」という刹那的なバブル時代の有象未曾有は平成の象徴でした。
中でも自身の家族を取り巻く記憶に関わるパブロ・ピカソ作《ピエレットの婚礼》の行方はバブル時代を物語っています。
泡のように消えてしまう時代の欲望は人魚姫のビジュアルに重ねられ、もの言わぬ誰かの視線と交差します。